はじめに
このページは、2021年2月9日に私のブログで公開した内容を編集したものです。「思い付いたから書いた」ものであり、日付に深い意味はありません。2021年7月2日に日本テレビ系列「金曜ロードショー」で「おおかみこどもの雨と雪」が放送されましたが、時期が近いだけで関係ありません。
当時、私がブログに掲載していたテレビ番組や映画のレビューの一環として書いたものです。2025年8月時点ではブログのテーマを「スマートフォン等のレビュー」に変更していますが、いまだにアクセス数が多いため、内容を編集して掲載を続けます。
「『おおかみこどもの雨と雪』はひどい映画だ」と批判しているわけではなく、「このような解釈も可能である」という趣旨です。
「発達障害」「マイノリティ」という言葉について
この記事は元々、映画「おおかみこどもの雨と雪」のストーリーを考察しつつ、「もしも雪と雨が人狼ではなく実在する人間ならば、発達障害がある子などのマイノリティに該当するのではないか?」という内容でした。映画のテーマが子育てであり、母親である花と「おおかみこども」である雪と雨の関係は、現実世界の「母親と、発達障害がある子」に最も近いと考えたためです。
現在は記事全体を見直し、文脈上必要なくなったため「発達障害」という言葉を使う箇所はほとんどなくなりましたが、文中の「狼」を「発達障害者などのマイノリティ」に置き換えて読むことは可能です。
ただ、その場合でも「架空の存在である『おおかみこども』を、実在する人間に置き換えて考える」ためであり、「現実世界のマイノリティは『おおかみこども』のような存在である」と主張しているわけではありません。
専門家による考察ではなく、医学的・学術的根拠もない
言い訳になりますが、このページの内容は「個人による映画『おおかみこどもの雨と雪』の感想」であり、社会的に何かを主張するものではありません。
私は発達障害に携わる医師、教師、学者等ではなく、発達障害を専門家レベルで理解しているわけではありません。その他のマイノリティ政策に携わる者でもありません。このページは医学的、教育学的な内容ではなく、この記事によって何らかの社会的提言を行うものではありません。
このページの「発達障害」はASDだけを想定していますが、本来、発達障害にはADHDとLDも含みます。
私自身にはASDに酷似する症状が多数あり、そのため発達障害に興味を持って書籍等で調べています。ただ、正確な診断は受けていないため、「当事者である」とは断言できません。「雨は私に似ている」と思っただけです。
「狼、獣人、人狼」という用語について
映画「おおかみこどもの雨と雪」の中では、「動物に化ける人間」や「人間と動物、両方の性質を持つ生物」は一貫して「おおかみおとこ」「おおかみこども」という言葉が使われており、「獣人」(beastman)「人狼」(werewolf)という表現は一切ありませんが、このページでは便宜上これらの言葉を使います。
また、映画の公式ウェブサイト等では「おおかみ」または「オオカミ」と仮名で表記されますが、このページでは「狼」と漢字でも表記します。文章の読みやすさ・理解しやすさを考慮したものであり、特別な理由はありません。「おおかみ」と「狼」は同じ意味です。
映画「おおかみこどもの雨と雪」のストーリー
2012年のアニメ映画「おおかみこどもの雨と雪」は次のようなストーリーです。
- 大学生の「花」は、ニホンオオカミと人間の間に生まれた「彼(おおかみおとこ)」(本名不明)と恋に落ち、女の子「雪」と男の子「雨」と産む。
- おおかみおとこと、その子である雪と雨は人間と狼のどちらにもなれる(いわゆる人狼、獣人)。
- おおかみおとこは花に食べさせる鳥を狩るために山に入り、事故死して下流に流される。
- 花はおおかみおとこの死体を発見するが、狼の姿だったので、ゴミ収集車に回収されてしまう。
- 花は都会(東京)を離れ、おおかみおとこの故郷(富山県)に近い村で古民家を改装して子育てする。
- 雪は狼らしく山を走り回り、臆病な雨は家で過ごすことが多くなる。
- ところが、成長するにつれて雪は人間らしくなる。雨は人間に馴染めず、狼として山でキツネの「先生」と一緒に過ごすことが多くなる。
- 雨は「人間としての自分」を受け入れられず、狼になって花たちと別れ、山で暮らす。
- 雪は、同級生の草平が「狼としての自分」を怖がらずに受け入れてくれたおかげで、人間として生きることに自信を持つ。
- 雪は私立中学校に進学する。花は一人で田舎に残り、山から響く雨の遠吠えを聞いて暮らす。
なお本筋とは関係ありませんが、成長した雪の声優は黒木華(くろき・はる)さんなんですね。気付きませんでした……。
「感動の子育てストーリー」なのか?
ストーリーだけサラッと読むと、「普通の人間である花が、(内縁の?)夫であるおおかみおとこと死別し、困難にめげずに子供二人を育て上げる感動の物語」ですし、映画のプロモーションでもそのような訴え方がなされています。
また、雨は立派に「成獣」して山で暮らすようになり、当初は思い悩んだ花も、雨の生き方を肯定します。
作中でもおおかみおとこ自身が「子供達を立派に育てた」ことを花に感謝しています。
ただ、「花がうまく子育てできなかったため、雨は人間社会に適応できず、人間社会を出て山に行った」とも考えられます。
現実世界に置き換えると、「発達障害を抱える子が人間社会で孤立し、親もうまく対処できず、施設に入れる」という状況です。
また、「狼の本能に目覚めた雨は人間社会では生きられないから、山で暮らすほうが幸せだ」という考え方は間違っています。幼少期は雪のほうが狼らしかったのに、人間として生活できているためです。
では、花の何が問題だったのか、雨はどうすれば良かったのか、具体的に考えていきます。
花は終始「『おおかみ』は異質な存在だ」という偏見を持っている
物語の主人公の一人である花は、「おおかみ」ではない普通の人間です。では、人間だと思っていた「おおかみおとこ」が狼だと知った時、花はどのような反応を示したでしょうか?
花はおおかみおとこに「怖くない……あなただから」と(おおかみおとこ自身に問われ)言いますが、言い換えると「あなたでなければ、怖い」となります。
つまり花は最初から「おおかみは怖い存在だけど、『おおかみおとこ』は愛する人だから耐えられる」と、「おおかみ」を異質な存在として捉えています。
花は「狼である雪と雨」を拒絶し、普通の人間として生きることを望んだ
花とおおかみおとこは、「生まれる子がどのような姿かわからない」という理由で、産婦人科には行かずに自宅での出産を選びます。
「獣人であると知られれば迫害されたり、実験動物にされたりするかもしれない」という懸念があったとはいえ、妊娠中から一貫して「おおかみこども」は「人間社会から隠蔽しなければならない存在」と捉えられています。
その後も花は、雪が移動図書館バスで狼になった時に慌てて頭を押さえるなど、雪と雨が狼である事実を徹底的に隠そうとし、「二人が狼になったらみんな驚くから、変身するのはやめようね」と諭します。
現実世界に置き換えると、親が、子供が抱える発達障害を隠そうとしたり、子供が急に大声を上げて走り出したり暴れたりするのをやめさせようとするようなものです。
もちろん、花は狼である二人が人間に危害を加えたり、反対に危害を加えられたりしないように「普通の人間を演じなさい」と教えたのであり、悪気はありません。
ですが結果的に「狼であることは人に知られてはならない、悪いことだ」と雪と雨に認識させてしまいましたし、前述のように花は「(愛する夫・子は例外だが)狼は怖い」と思っています。
他者との違いを認識しなければ悩まずに済む
繰り返しますが、花が二人を愛していることは間違いありません。付け加えると、当初は戸惑いながらもさほど悩まず子育てを楽しんでいました。
人付き合いが少なく他の子達と比較しなかったので、雪と雨が一般的な人間とは異なることを認識する機会が少なかったためです。
花と、狼になった雪と雨が雪山で遊ぶシーンが、最後の「親子三人で過ごした楽しい時間」ですね。
雪山から帰ろうとする時、雨が鳥を狩ろうとして川に落ち溺れかけてしまい、花は強い恐怖を覚えます。
花は、「雨が死んだらどうしよう」と不安になると同時に、「狼として生きるのは危険だし、普通ではない。人間として生きてほしい」とそれまで以上に思うようになったのではないでしょうか。
現実でも、落ち着きがない子供は事故に遭いやすくなるおそれがありますし、他者とのコミュニケーションが苦手ならばトラブルを招くこともあります。
そして雨が小学校に入り、不登校になると、花は人間社会の中での雨の立場を認識し「雨は『普通の子』とは違う」という思いを強めます。
花と雨を決別させた出来事
不登校になってしばらく経つと、雨は「雪も山に来たらいいよ」と提案し、「自分は人間だ」と思いたがっている雪と大喧嘩します。
花は喧嘩を止めようとし、落ち着いた後に家を片付けながら「雪と雨は自分の道を歩もうとしている」と考えます。
花は喧嘩の直後に雨に声をかけただけで話し合うことはできず、「狼の道に進む雨」を止められませんでした。
ただ、花は「雨の選択を尊重した」というより、「手に負えなくなって諦めた」のではないでしょうか。
この場面の雨は目が光る「人間ではない異質な存在」として描かれており、花と雨の双方が「ただの人間である花と、狼である雨はまったく別だ」と思うようになり、理解し合うことを諦めたように見えます。
「狼は狼らしく、人間から離れて自然で生きるべき」という偏見
ストーリーを遡りますが、おおかみおとこの死後、自宅に児童相談所の職員が押しかけてきたこともあり、花は都会から「おおかみおとこ」の故郷の近くに引っ越して子育てします。
単に人が多い都会から逃げたわけではなく、作中では花が「二人を自然の中で育てて、人間と狼のどちらの生き方も選べるようにしたい」と考えたことが明示されます。
ここで花は「狼は人間社会から離れて自然の中で生きるものだ」と考えていますが、これは先入観や偏見の類です。
なぜなら、現実でも動物園や飼育施設、個人の住宅で飼われて人間と一緒に生活する狼(または狼犬)は存在し、彼らが「自分は狼だから、人間と共存できない。自然の中で生きたい」と考えることはないからです(逃げることはあります)。
余談ですが、「哲学者とオオカミ: 愛・死・幸福についてのレッスン」という本には、マイアミ大学の哲学教授である著者が、幼い狼を飼い、長年自宅や大学キャンパスで一緒に過ごす様子が記されています。
「狼が人間と一緒に暮らすのは特殊な例だ。人間に危害を加えるかもしれない」という考え方は正しいのですが、雨はただの狼ではなく獣人ですし、人間同士でも暴力を振るうことはあるので狼だけが危険なわけではありません。
花が狼である雪と雨に対し「狼はこうやって生きるのが狼らしいのだ」という先入観・偏見を抱いたのは、本物の狼(獣人)と交流した経験が少なく、ステレオタイプを当てはめるしかなかったためです。
たとえば、現実でも日本人が「○○国の人はこのような性質で、日本人とは全く異なるのだ」と、噂話や思い込み、ステレオタイプによる偏見を抱くことがあります。
ところが、その国の人との交流を重ねると、日本人とあまり変わらないことがわかり、偏見を払拭できます(必ずではありませんが)。
発達障害についても同じことで、医師などの専門家の助けがなければ、親は「発達障害の子にはこういう特性があるから、発達障害がない子と同じようには生きられないんだ」と偏見・思い込みを持ち、思い悩んだり、「発達障害者らしい生き方」を押し付けたりするかもしれません。
作中の花は、「おおかみおとこ」と雪と雨以外では、「新川自然観察の森」で飼われている狼に短時間会ったことを除けば本物の狼と交流する機会がなく(「獣人」に限定すれば皆無)、最後まで偏見を正せませんでした。
「二つの生き方から一つを選ぶ」ことはできない
また、「二つの生き方から一つを選ばせる」という花の考えにも問題があります。
なぜなら、雪と雨は一生「人間かつ狼である存在」として生き続け、どちらか片方だけを選ぶことはできないためです。
それにもかかわらず、人間と狼という二つのアイデンティティの片方だけを選ばせようとすると、もう片方が抑圧されることになります。
花は雪と雨に「狼であることを隠しなさい」と教えて育てたため、二人の狼としてのアイデンティティは既に抑圧されています(正確には、後述のように小学校入学前後に既に抑圧された状態で狼のアイデンティティが生じます)。
さらに、花は人間と狼という二つの生き方を提示しつつ、実際は雪と雨が普通の人間として育つことを望んでいます。
終盤に雨が狼として山に去ろうとして花が引き留めるシーンで表現されたように、「狼として生きる」ことは「人間社会からの離脱」を意味しているため(「狼は人間と共存できない」という、花と雨の思い込みが原因です)、花にとって望ましいことではありません。
その結果、雨はかえって狼のアイデンティティに固執するようになり、反対に人間のアイデンティティを否定するようになりました。
しかし、花は雨の狼のアイデンティティを否定せず、作中のように狼としての雨を見送ったりもせず、「雨は人間であり、狼でもあるから、どちらか一方の面を否定せずに両方とも受け入れよう」と考えることもできたはずです。
そうすれば、雨は「自分は狼だから、人間と離れて生きなければならない」と思い込まず、成長してからも、ある時は人間である時は狼として生きられたのではないでしょうか。
実際に幼少期には雪と雨は人間かつ狼として生活していたのですから、「成長したら、人間と狼のどちらか片方を選ばなければならない」などということはありません。
花はそんなに悪いのか?
ここで花を擁護すると、「雪と雨には狼であることを隠し、普通の人間として生きてほしい」という願いは、彼女の立場から見れば間違ってはいません。
自身は普通の人間であり、子育てが初めてで、しかも夫に死なれた花が、「普通の人間が『人間と狼の両方である存在』を目にしたら怖がる。そんな存在は人間社会で生きられないから、二人が人間として生きられるように育ててあげよう。それができなければ、狼として自然の中で生きさせてあげよう」と考えても無理はありません。
また、前述のように狼と接した経験が少ない花が「狼とはこのように生きるものだ」と思い込むのも、やむを得ないとは言えるでしょう。
「獣人の育て方」を学べればそうはならなかったのでしょうが、お父さんの「おおかみおとこ」は死んでしまいました。
普通の子育てでも大変なのに、獣人を誰にも相談できず一人で苦労して育てたら、疲れ果て、雨が人間として生きさせるのを諦めても無理はないでしょう。
最終的に花は雨の「狼として生きる」という選択を受け入れ、彼の遠吠えを聞いて微笑みを浮かべるまでになります。
しかしこれは、「息子と一緒に暮らしていた時は怖くて辛かったが、離れて暮らし始めて気楽になった母親」の姿であり、共生を諦めたも同然です。
雨は「狼のアイデンティティ」を抑圧され、「人間としての自分」を否定した
次に、母親の花ではなく、子である雪と雨の視点で考察します。
幼い頃、小学校に入るまでの雪と雨は、「狼であることを隠しなさい」という花の言いつけを守りながらも、特に悩むことなく楽しく過ごしていました。
前述の「雨が、雪山で鳥を狩ろうとして溺れかける場面」は「雨が狼の野性に目覚めたきっかけ」として描かれますが、実際は小学校に入る前の雪のほうがはるかに狼らしかったため、雨を変えた最大の出来事とまでは言えません。
雨にとってのより大きな変化は、小学校で同級生(上級生?)にいじめられて不登校になったことです。
この出来事により雨は「僕は人間に馴染めないから、人間ではなく狼なんだ」という思いを強めていきます。
「狼のアイデンティティ」に固執する雨
アイデンティティは生まれながらにして個人の人格に備わったものではありません。他者との比較により生まれる「自分は、社会の中でこのような人間である」という自己認識です。
たとえば、仮にすべての人間が同じ性別ならば、「男性・女性」というアイデンティティは存在しません。
自分達が「普通の人間」ではないと気付いた雪と雨には、「自分達は人間ではない」という否定的な「狼としてのアイデンティティ」が発生します。
しかし二人は人間としても生きられるため、同時に「人間としてのアイデンティティ」も生じ、二つのアイデンティティが併存します。
前述のように、雪と雨は一生、人間と同時に狼でもあり続けるので、どちらか片方のアイデンティティだけを選んで生きることはできません。
ところが、雨は花のしつけや「狼が悪者の童話」に抑圧されてきたこともあって、手に入れた狼のアイデンティティに執着します。
人間としての自分を否定するため、「自分は人間ではなく狼だから、人間から離れて自然の中で生きなければならない」という自己ステレオタイプ化に陥り(花が教えたわけではないのに、偶然にも彼女と同じ認識です)、必要以上に「狼であることにこだわる」ようになります。
最終的に、死を迎えた「キツネの先生」に代わって山を守るという、彼自身が思い描いた理想の狼として生きることを選びますが、雨が否定した人間としてのアイデンティティは残っています。
雨は「人間だからこそ」狼として生きることを願った
作中の雨自身も、おそらく映画の製作者も認識していないはずですが、「雨が『狼として生きたい』と願ったのは、雨が人間だから」です。
雪や雨のような獣人ではなく、現実世界に存在する本物の動物は、「自分は狼だから、狼らしく生きなければならない」と考えたりしません。アイデンティティは人間特有の概念であり、動物には存在しないためです。
もちろん、動物にも自分の縄張りや群れ(家族)を守りたいという感情や、強くなりたい、恋愛相手に魅力的に見られたいといった欲求はありますが、人間のアイデンティティとは異なります。
「ライオンの映画」のように特定の動物がその地域一帯の王として秩序を司ったり、「生き物の命は循環する」「食べる時以外は、生き物を殺してはならない」と考えたりするのは、人間の想像上の動物しか持たない倫理観・アイデンティティです。
人間は、「社会の中で自分はどのような属性(ジェンダー、年齢に合う行動、職業、宗教、政治思想)を持つか」を他者との比較によりアイデンティティとして身に付け、自分自身の願望や社会からの要請により強化します。
「人間社会を離れて狼として生きる雨」は「人間である雨自身が、『人間である自分』を否定するために思い描いた理想の狼」です。
雨が本当に狼ならばアイデンティティに固執せず、家で花と一緒に暮らしながら時々山に行って気楽に生きたでしょうし、獣人である雨も最後までそのように生きられたはずです。
雪は理解者・草平に出会い、二つのアイデンティティを受け入れられた
一方で雪は、一時期は雨と同様にアイデンティティに悩み、彼と大喧嘩を繰り広げるものの、最終的には悩むことなく生きられるようになります。
作中では「雪は人間として生きることを選んだ」ことが描写されていますが、私の解釈は異なります。
ここまで述べたように、雪も雨も、一生、人間と狼の両方であり続けるからです。また、一度生じたアイデンティティはめったに消えないので、表面的には人間と狼の片方を選んだように見えても、人格の内部では両者が併存しています。
では、なぜ雪は狼であることに悩まずに人間として生きられたのでしょうか?
友達と関わり、「群れのルール」を学んだ雪
当初、雪は雨よりも狼らしい子で、田畑を走り回って小動物や虫を狩ったりしていました。
ところが、小学校に入って友達に(狼であることは隠して)狩った動物や虫を見せて気味悪がられ、「友達に嫌われたくない」という気持ちから狼らしい行動を控えるようになります。
実は、この雪の変化こそ狼らしいと言えます。なぜなら、雪は友達という「群れ」のルールを学んだためです。
現実の動物は、飼い主や群れのメンバーに注意されることでルールを学んでいきます。嫌がったり、しつけがうまくいかなかったりすることはありますが、「自分は狼なのに、なぜ狼らしい行動をしてはいけないんだ!」と思ったりはしません。
雪は、(人間だから持つ)狼のアイデンティティに固執せず動物のようにルールを学んだため、うまく人間に適合できたと言えます。雨とは対照的です。
現実の人間も、動物のように単純にルールを学ぶわけではないにせよ、「親や友達を困らせるから、あまり大声を出さないようにしよう」などと考え、学習することができます。
その後も雪がアイデンティティに悩む様子はことさら描かれることなく、転校生・草平との出会いにつながります。
ありのままの雪に接した草平
転校してきたばかりの草平は雪に興味を示し、本人に向かって「獣臭い」と言って追い回し、怒った雪に狼の爪で引っかかれます。
狼のアイデンティティに固執した雨とは対照的に、雪は友達に気味悪がられたり、「人間か、狼か」で雨と大喧嘩したこともあって、「狼としての自分」を否定しようとしていました。
雪は狼の性質を見せてしまったことにショックを受けて泣きますが、草平は雪を責めず、親に「(怪我は)狼がやった」と告げます。
その後も草平は雪が狼だとばらそうとしたり、彼女を責めたりせず、普通に接してくれます。
そして、雨が山に旅立った嵐の夜、雪は草平の前で狼の姿になりますが、「わかってた。誰にも言わない。泣くな」と話し、そのままの雪を受け入れてくれます。
草平にとって雪は雪であり、人間か狼かは重要ではない、ということではないでしょうか?
自分が狼であることに悩んでアイデンティティを否定してきた雪は、草平のおかげで「私は人間で、狼でもあるから、どちらか片方を否定しなくていいんだ」と、アイデンティティに悩むことがなくなりました。
繰り返しますが、雪と雨は生まれながらにして「人間であると同時に狼である獣人」であり、自分の意思でやめることはできませんし、表面的には片方を選んだように見えても両者のアイデンティティが残っています。
雪の場合は、雨とは逆に狼のアイデンティティを否定し、人間としてのアイデンティティを重視していました(雨とは異なり、「固執」というほどではありません)。
しかし、草平という理解者に出会って「人間と狼、一方だけのアイデンティティを選ぶ」という必要性がなくなったため、両方のアイデンティティを自然に受け入れられるようになったと言えるでしょう。
確かに、雪は映画の最後で「完全に人間になった」ように見えますが、「特に狼になりたいとは思わない、その必要がない」だけであって、「人間として生きることを選び、狼のアイデンティティを否定した」わけではありません。
花と雨はどうすれば良かったのか?
雪は草平という理解者に出会って二つのアイデンティティを受け入れられたので良かったのですが、花と雨は「狼は人間とは異なる存在で共存できないから、狼は人間から離れて生きなければならない。雪と雨は、人間と狼という二つの生き方から片方だけを選ばなければならない」と思い込み、雨は「(人間である彼が想像した)理想的な狼」になるために人間社会を離れて山で生きるようになりました。
最後に、花と雨が誤った思い込みをやめて「人間であり、狼でもある獣人」として生き続けるためにはどうすれば良かったのかを考えます。
「おおかみおとこ」がお父さんとして生き方を教える
ここまで「花は獣人の育て方を知らなかったし、狼に会ったこともほとんどなかったので『狼は自然の中で人間と関わらず生きるものだ』と思い込み、雪と雨に二つの生き方を選択肢として提示しつつ人間として生きることを望んだ」と書いてきました。
ならば、獣人として成長してきた「おおかみおとこ」が、父親として生き方を教えれば良いのです。
花の「狼は自然の中で人間から離れて生きる」「雪と雨は、人間と狼の二つから片方の生き方を選ばなければならない」という考えとは裏腹に、「おおかみおとこ」は普通の人間である親戚に正体を知られずに育てられ(無理では?)、トラックドライバーとして働いていました。しかも、時々狼になって山で狩りをしていました。
彼がどのように育ったかは作中で描写されていませんが、雨のように「人間のアイデンティを否定し、抑圧された狼のアイデンティティに固執する」ことはなかったはずです。
雨が一人で思い悩んだのは、「思春期に『同性の親』から生き方を教わることができずに『自分は異質な存在になった』と感じ、それを否定して隠そうとしながらも執着してしまう」ようなものです。
ですから、お父さんの「おおかみおとこ」が生き方を教えれば問題は起きません。ただ、映画と同じく彼が死んでしまった場合のことも考えましょう。
狼であることを隠す必要はなかった
雨が狼としてのアイデンティティに固執するようになったのは、花に「狼であることを隠しなさい」と教えられたのが一つのきっかけです。
子供が親に「遊ぶのをやめなさい!」と言われて反発するように、狼のアイデンティティを否定された雨は、かえってそれにこだわるようになりました。
それならば、花は雪と雨が狼であることを隠さずに、堂々と公開すれば良かったのです。
花が心配したように、捕まって実験されることはないでしょう。まず科学者が「人間と狼の両方になれる生物がいる」ことを信じるはずがありませんし、仮に信じる科学者がいても、雪と雨は人間でもある以上、非人道的な実験は行えないためです。
狼であることを「気味が悪い、怖い」と思って差別する人間もいるかもしれませんが、理解してくれない人は放っておけば良いのです。
作中ではまったくパソコンや携帯電話(スマートフォン)が描写されていませんが、現代ではインターネットを使って他者と交流できるのですから、「地域コミュニティ」を意識する必要もありません。
最初から人間であり狼でもあると明かしておけば、「人間と狼、どちらか片方だけの生き方を選ばせる」ことも、「人間と狼という二つのアイデンティティに悩む」こともありませんでしたし、花が誰かに子育てについて相談することだってできたでしょう。
もしかしたら、雨にも雪にとっての草平のような理解者が現れたかもしれませんし、中には「狼になれるなんてかっこいい!」と思う人もいることでしょう。
いずれにせよ、「秘密がバレたり、傷付けたり、傷付けられたりしたらどうしよう」と悩むより、他人に迷惑をかけても気にしないくらいがちょうど良いのです。
「人間はそんなことしないから」という理由で、雪と雨が走り回ったり遠吠えしたりするのをやめさせたりする必要はありません。
それでも雨が孤立してしまったら、花は…
たとえ雨が「二つのアイデンティティ」に悩まず、花が「二つの生き方」を選ばせなかったとしても、雨が孤立しないという保証はありません。映画のように、同級生にいじめられて不登校になるかもしれません。
その場合、花はどのように接するべきでしょうか? それは、雨の行動を否定せずに見守ることです。
作中、雨は学校に行かず家で本で読んだり(これは人間特有の行動ですね)、山で「先生」と呼ぶ野生のキツネと過ごしたりするようになりました。
そんな雨を見て「狼として生きるならば、人間としては生きられなくなる」などという偏見を抱いたりせず、雪に対する草平のように、人間であり狼でもある雨にそのまま接すれば良いのです。
雨が山で動物を狩ってきたら、花は「うまく狩りができるようになったね」と笑顔で接してあげれば良いでしょう。雨の狼としてのアイデンティティを否定しなければ、彼がそれに固執することもありません。
成長するにつれて、花は「雨は人間でもあるのに、学校にも仕事にも行かなくて良いのだろうか?」と心配になるかもしれませんが、「普通の人間らしい生き方」を押し付けず、雨がしたいことを見付けるのを気長に待ったほうが良いと思います。
もしも、花がどうしてもそうできないのであれば、信頼できる人に相談するしかありません。よって、雨が狼であることはどうやっても明かさなければならなくなりますが、雨のためを思うなら世間体や恥ずかしさを感じるべきではありません。
映画と同じく雨が完全に花から離れて山で暮らすようになることもあり得ますが、花がこのように行動すれば、そうはならないと考えます。
雨は「母さんは僕を否定せずに見守ってくれるんだ」と思い、山で過ごしつつも、古民家で花と一緒に暮らし続けるのではないでしょうか。
そうすれば、雨は父親である「おおかみおとこ」のように、人間としての自分を否定せずに狼として山で過ごすことができます。
アイデンティティにとらわれる必要はない!
映画の最後、花は狼になって山に去る雨に「強く生きて」と呼びかけます。
しかしこの時の雨は、強いどころか、「人間であるが故に『狼のアイデンティティ』に固執し、自分で自分を縛り付けた弱い存在」です。
映画の中の雨に限らず、人間は「自分はこのようなアイデンティティを持つから、その通りに生きなければならない」と思って生きています。男だから、女だから、若者だから、高齢者だから、日本人だから……などです。
社会からの要請によってアイデンティティを受け入れれば社会でうまく生きられますし、「日本人で良かった」というふうに心地良くなることもあるかもしれません。
ただ、アイデンティティに固執することは、自分自身にレッテルを貼る行為であり、自分自身がアイデンティティから逸脱することを許せなくなります。
そして、マジョリティがアイデンティティに固執しても社会に受け入れられるので不都合は生じませんが、発達障害者や外国人、性的少数者や少数派の宗教を信じる人などのマイノリティであれば、アイデンティティによってマイノリティとの違いを強く意識することになります。
さらに、アイデンティティを抑圧されることで、雨のように固執して「マジョリティからかけ離れた、理想のマイノリティである自分」になろうと過剰に行動することもあるでしょう。
「自分が社会で生きづらいのは、発達障害があるからだ!」と思い悩み、そのアイデンティティに固執して自己ステレオタイプ化に陥り、さらにそのアイデンティティに合致した人間になろうとする……ということです。
ただ、誰にでも、マジョリティであっても、社会でうまく生きられないことや他者と対立することはあります。社会で孤立して苦しむのは、マイノリティとしての特性やアイデンティティが原因であるとは限りません。
もしもアイデンティティが原因で苦しんでいるならば、「自分は何者なのか」と考えるのをやめたほうが良いのではないでしょうか。自分が何者かを考えなくても生きられます。
また、他者が「お前はマイノリティだからこうなんだろう」とレッテルを貼ってきたら、無視すれば済むだけです。
人格を支えて誇りになってくれるはずのアイデンティティが、かえってその人を苦しめてしまうのは悲しいことです。
たとえ考えるのをやめたとしても、アイデンティティが人格から消えることはなく、否定したことにはなりません。肯定的に受け入れられるようになるまで、一旦脇に置いておくだけです。
雨も、狼であることにこだわり続けて苦しむのではなく、もっと気楽に楽しく生きれば良かったのにな、と今でも思います。



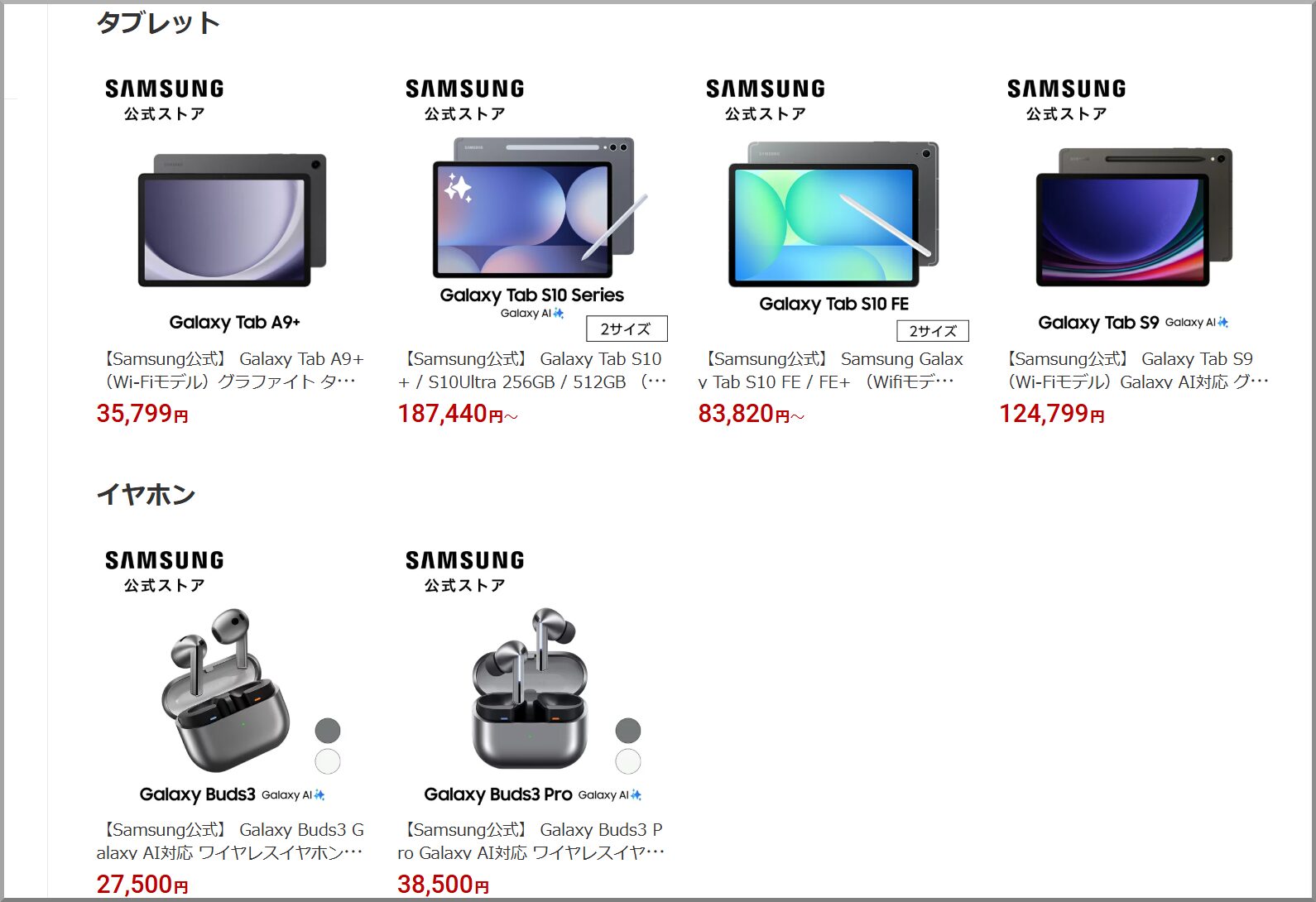

コメント